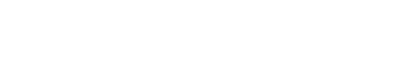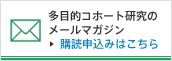多目的コホート研究(JPHC Study)
2009/9/4 飲酒と循環器疾患発症との関連への社会的な支えの影響について
JPHC研究からの論文発表のお知らせ
多目的コホート(JPHC)研究から、飲酒と循環器疾患 の関連に、社会的な支えがどのように影響するのかを調べた研究の結果が発表さ れました。論文の状況は以下の通りです。
Alcoholism: Clinical and Experimental Research 2009年 WEB先行公開
飲酒と循環器疾患発症
これまでの研究から、飲酒は脳卒中のリスクを増加させるのに対し、虚血性心 疾患のリスクを低下させることが知られています。
多目的コホートで40〜69歳の男性約1万9,000人の方々を約10年間追跡したとこ ろ、やはり飲酒は虚血性心疾患の発症リスクの低下と関連する一方、エタノール 換算で週に300g以上の大量飲酒では脳卒中の発症リスクの増加が認められ、タイ プ別には特に出血性脳卒中のリスクが高くなっていました。
※ エタノール換算で週に300gというと、1日当たりの飲酒量のおよその 目安として、日本酒なら2合、ビールなら大瓶2本、焼酎なら1.2合、泡盛なら1 合、ワインならグラス4杯、ウィスキーならダブル2杯程度という計算になります。
週に1-299gの少量〜中等量の飲酒には社会的な支えによる好影響
多目的コホート研究では、これまでに社会的な支えが多いほど脳卒中の死亡リ スクが低いことを報告しています。飲酒には社会的な付き合いを円滑にするため の手段という側面もあります。
そこで、社会的支えのスコアを用いて、飲酒と循環器疾患の発症との関連が、 社会的な支えの状況によって異なるかどうか検討しました。
すると、飲酒量が少量〜中等量のグループ(エタノール換算で週に1〜299g) では、社会的な支えが多い場合は脳卒中の発症リスクが飲まないグループに比べ て低いのですが、支えが少ない場合には、約1.2〜1.8倍と高いことがわかりまし た。それ以上の大量飲酒では社会的な支えによる好影響はみられませんでした。
研究の結果について
飲酒量による循環器病発症リスクを正確に比べるために、把握できている他の 要因(年齢・喫煙、BMI、血圧、糖尿病既往、レジャー時の運動、精神的ストレ スなど)についての飲酒グループ間の差がないように調整して比較しましたが、 調整しきれない部分や、把握できなかった部分が残ってしまい、それが結果に影 響した可能性があります。
循環器疾患の予防のためには、大量飲酒は慎むべきです。また、これまでの飲 酒についての結果からも、健康維持のためには、「節酒」と「休肝日」を組み合 わせた飲酒習慣を実行することが重要です。
詳しくは、ホームページに掲載された概要版および詳細版をご覧ください。
・飲酒と循環器疾患発症との関連への社会的な支えの影響 —概要—